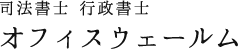よくある質問
- ホーム
- よくある質問
- Q
相続の手続きは、何からスタートすればよいのでしょうか?
- A
まずは「相続人は誰か」「遺言書の有無」「財産の把握」の確認を行います。
相続人を把握するには戸籍謄本を確認するのが確実です。当事務所は戸籍謄本の取得から行っておりますのでワンストップでご対応が可能です。
- Q
相続財産に含まれるものはどんなものがありますか?
- A
現金、預金、不動産、債権、車、家具、宝飾品といったプラスの財産や借金、買掛金、未払いの税金・家賃といったマイナスとなる財産が含まれます。
- Q
財産の中に借金がありました。借金も相続しなければいけませんか?
- A
原則として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
ただし、相続自体を放棄した場合やプラスの財産内でマイナスの財産を引き継ぐ方法もございます。
- Q
遺言書があった場合は必ず遺言書の内容を守らないといけませんか?
- A
相続人全員が合意すれば遺言書と異なる遺産分割が可能です。
- Q
遺言書がない場合、相続はどうなりますか?
- A
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、分割方法を決めるようになります。
- Q
相続人の中に未成年がいる場合はどうなりますか?
- A
親権者である親が法定代理人として相続手続きを行います。
ただし親権者自身が相続人の場合、利益相反となるため手続きは行えません。
この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を依頼し、選任された特別代理人が相続手続きを行います。
- Q
養育費の取り決めの際に気をつけることはありますか?
- A
必ず書面で残しましょう。
正式な書類(公正証書)を用意しておくことで相手が払ってくれない時に相手の給料(手取り額の半分)などを差し押さえることができます。
公正証書の制作も当事務所にお任せください。
- Q
別居中でも養育費の請求はできますか?
- A
婚姻中は子どもと配偶者への扶養義務が発生しますので、養育費ではなく、子どもと配偶者分の生活費の請求が可能です。
- Q
養育費はいつからもらえますか?
- A
離婚成立後から請求することができます。 養育費の取り決めを事前にしていないと相手方との金額の折り合いをつけるのに時間がかかる可能性もあるため離婚前に取り決めをしておくとスムーズです。
- Q
養育費はあとから請求できますか?
- A
離婚当時は養育費が不要でも、事情が変われば必要になることもあると思います。
そのような場合は請求することができます。ただ離婚当時に養育費は不要という約束をしてしまっていた場合は相手方も養育費の支払いが不要なうえで生計を立てている場合がほとんどなので協議が難航するケースもあります。
折り合いがつかない場合は調停を申し込むこともできますが事情を相手方に理解してもらうのが大切です。
- Q
取り決めた養育費よりも少ない額しかもらえません・・
- A
このような場合は不足分を請求することができます。
お一人で悩まず当事務所へご相談ください。
- Q
事業承継をする際に注意点はありますか?
- A
できるだけ早い段階から準備を進めることをお勧めします。 適切な後継者の選任や、固定資産税、借入金の引き継ぎなどに時間がかかるのはもちろんのこと、会社の未来がかかった大きな決定ですので余裕をもって行うことが大切です。
- Q
事業承継にはどれくらいの年数がかかりますか?
- A
後継者の育成や事前準備をどれだけ行っているかによって変わってきますが一般的には数年~10年程が目安となります。
- Q
事業承継をすることを決めたわけではないのですが相談は可能でしょうか?
- A
可能でございます。早めにご相談いただくことでより良い意思決定ができると思いますのでお気軽にご相談ください。